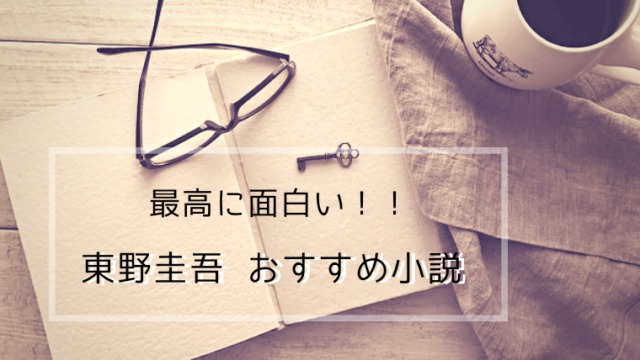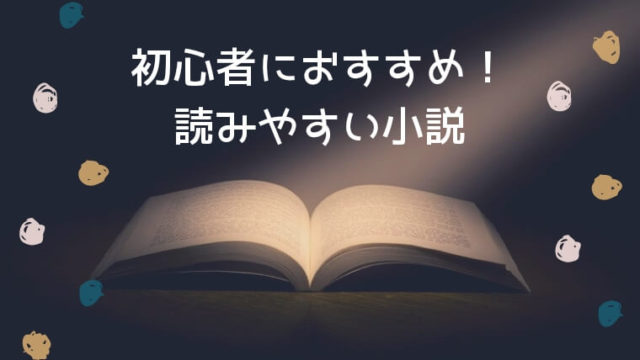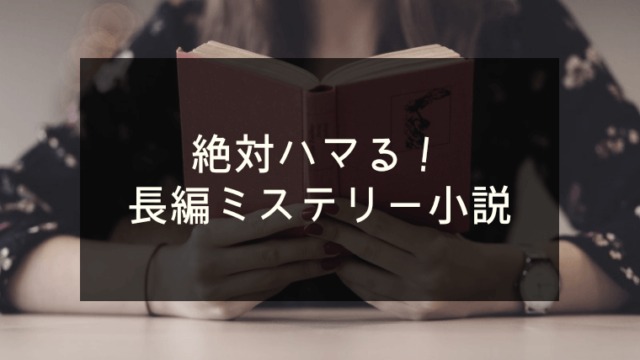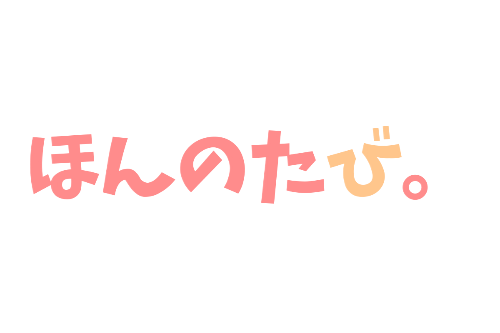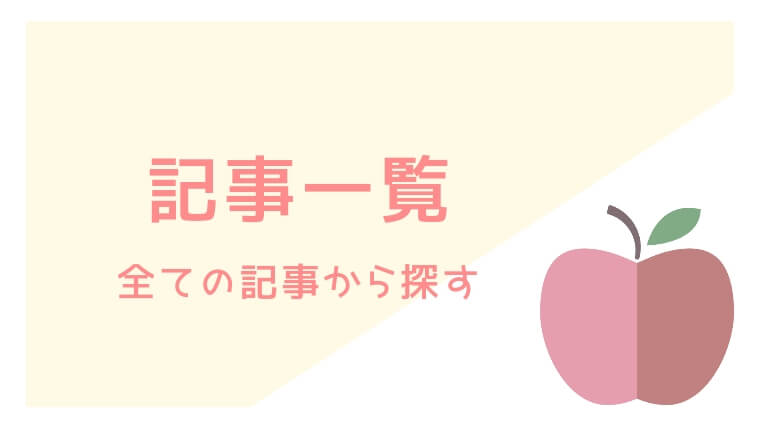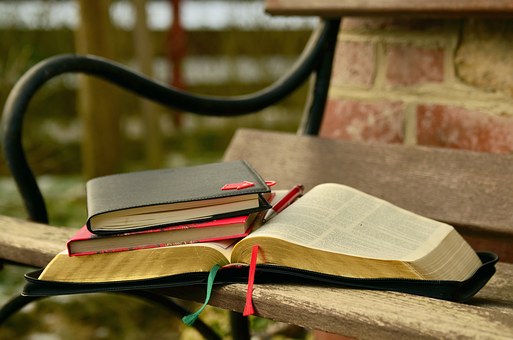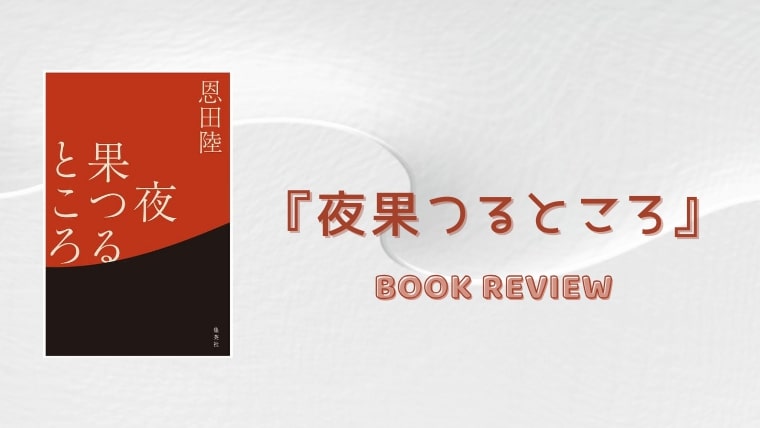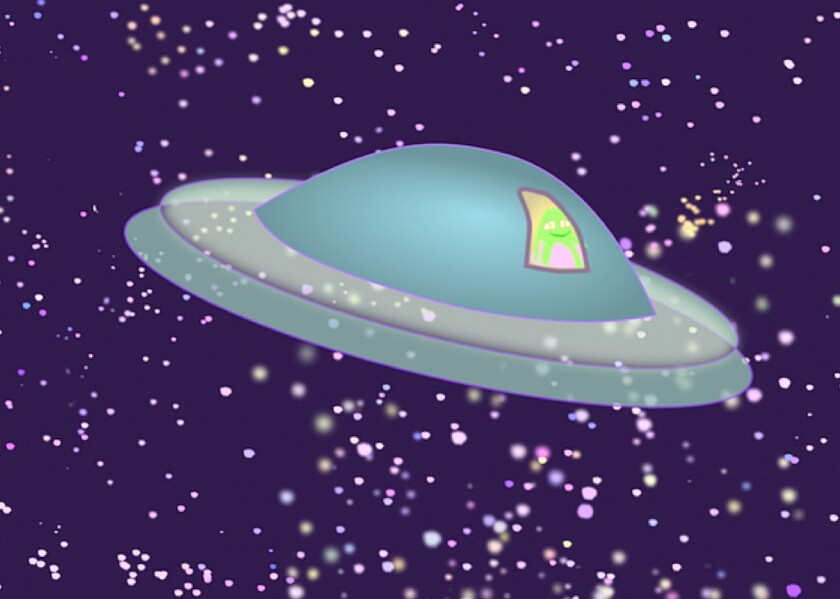『人魚の眠る家』あらすじ・ネタバレ感想文|止まった時間と奇跡の子供|東野圭吾

- 『人魚の眠る家』あらすじと感想文
- 残酷な現実
- 脳死と臓器提供
- 母の愛と狂気
- 救われた命
少しだけネタバレあります。
母の狂気と愛。その先にあるのは―。
東野圭吾さん『人魚の眠る家』感想です。前半はあまりにも悲しくて目が潤みました。でも読み進めるにつれてだんだんと寒気がしてきます。
とつぜん家族をおそった悲劇。

重いテーマでもサクサク読めたよ。
『人魚の眠る家』あらすじ
母の狂気と愛を感じた小説
仮面夫婦の播磨和昌と薫子の娘・瑞穂が、プールでおぼれて病院に運ばれた。彼らは急いでかけつけるが、待ちうけていたいたのは・・・。
『人魚の眠る家』ネタバレ感想文
『人魚の眠る家』テーマは脳死と臓器提供。そして母の愛と狂気です。
一種のホラーにも思えてしまったけど、母の愛を感じる物語でした。娘の死という受けいれ難い現実が全てのはじまりです。
残酷な現実

播磨和昌と薫子の娘・瑞穂は、プールでおぼれて病院に運ばれます。播磨夫妻は急いでかけつけるのだけど、そこで待ちうけていたいたのは・・・
娘の脳死。その可能性が極めて高いという事実でした。

あまりにも残酷な現実。
医師・進藤先生から告げられた言葉に言葉を失いました。回復の見込みはないと・・・。
このような状態に陥った場合に出てくるのが臓器提供です。それも娘の状態を知らされた直後にその話が出てきてびっくりしました。
脳死と臓器提供
脳死を考えるとき、人の死は何をもってそう判断するのか。
脳なのか、心臓なのか。脳が死んでも心臓は動いています。魂がどこに宿っているかという考え方一つでかわってきますよね。
以前よんだ中山七里さんの『切り裂きジャックの告白』でも扱っていたテーマでした。

海外の国では、ほとんどがそれは人の死だとされていて移植が行われているみたい。
日本の法律では、臓器提供する意思があった場合に限り「脳死を人の死」としています。・・・それによって生じる問題もあるのだけど、それは後ほど。
播磨夫妻は臓器提供を拒み、娘の延命を望みます。その決断は誰にも否定できるものではないですね。
臓器提供を決断すれば誰かの命が助かるのかもしれません。でもまだ温かい我が子が死んでいるなんて思えない・・・。

自分が同じ立場になったら・・・と、考えたよ。
母の愛と狂気

最初は瑞穂の母・薫子に感情移入していました。
延命を望んだ彼女は、眠ったままの瑞穂を家で介護します。夫の和昌の部下・星野祐也とともにあることを施すのだけど・・・。少し行きすぎていて狂気のような怖さも感じます。
星野はBMIの研究をしていました。
東野さんの得意分野・科学の登場です。コントロールをすれば瑞穂の手足が動くようになる。これが徐々に薫子を狂わせていきました。
祖父に反対されても延命措置を続ける夫妻。そこにあるのは娘への愛情です。だから余計に切なくなるんですよね。・・・でも強さも感じました。

守るべきものがあると、人は強くなれるんだ。
臓器移植の壁
先ほど臓器移植における日本の法律について書きました。『人魚の眠る家』には、それによって起こりえる問題も描かれています。
あるひとりの少女・雪乃は心臓移植を望んでいたが、国内ではドナーが限りなくゼロに近いため、莫大なお金を払って海外に行くしかないということ。

法律によって生じる壁だね。
日本では臓器提供をする意思があって初めて脳死判定がされるのです。そのためにドナーの申し出がないという現状があります。
でもこの問題は簡単にクリアできるものではないですね。命の定義に関わってくるものだから・・・。

東野さんの小説は、今回も深く重い問を投げかけてきた。
『人魚の眠る家』救われた命と結末
重いテーマが続いていたけど、結末は良かったです。播磨夫妻の決断が人の命を救いました!
人魚のような瑞穂は、まさに奇跡の子供だったのです。

救われた気持ちになったよ。
眠ったままの女の子は、それでも幸せな時を過ごしたのでしょうね。最後に救われました。