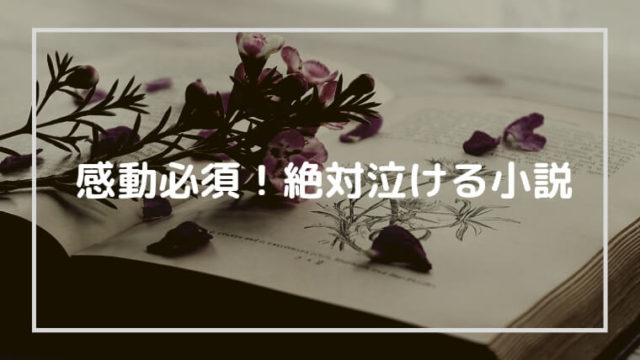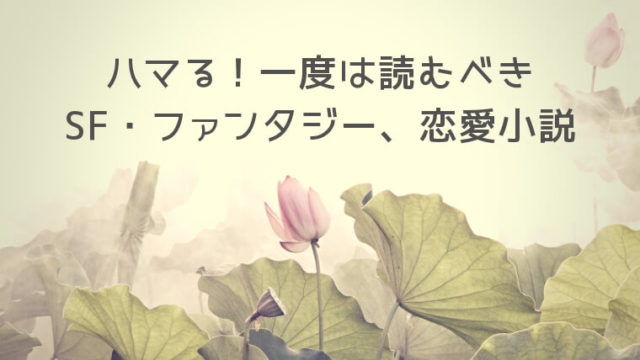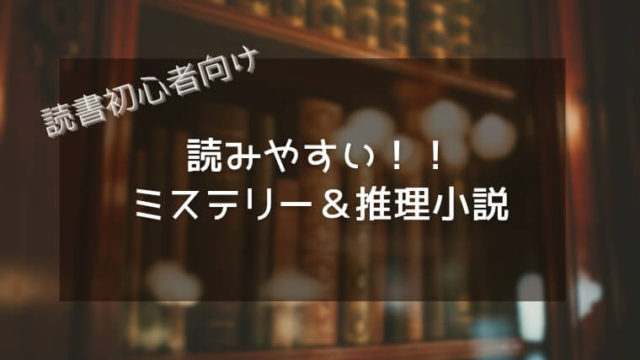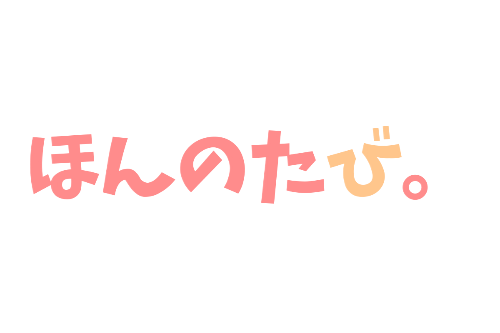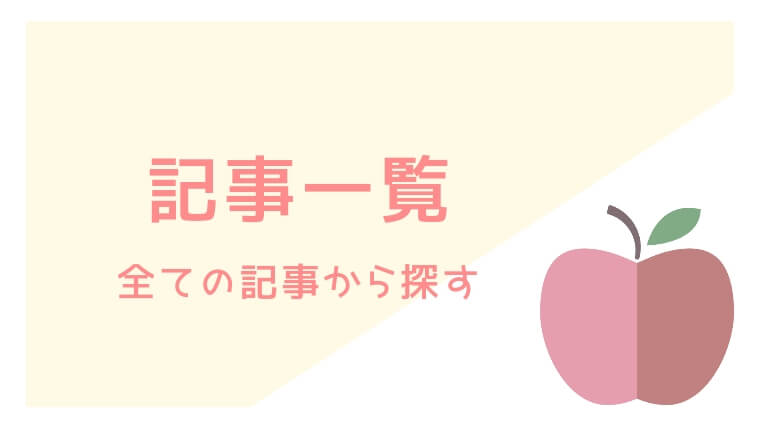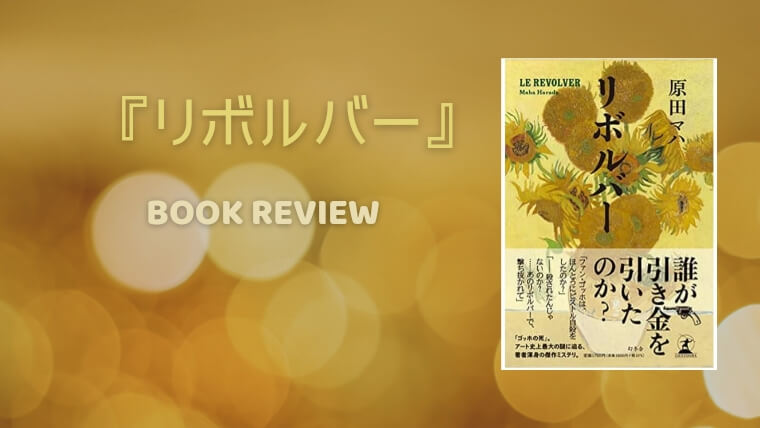『スロウハイツの神様』あらすじとネタバレ感想文|チヨダ・コーキに号泣|辻村深月

- 『スロウハイツの神様』あらすじと感想文
- 「二十代の千代田公輝は死にたかった」 について
- スロウハイツの住人たち (登場人物)
- チヨダ・コーキについて
- コーキの天使ちゃん
少しだけネタバレあります。
いいことも悪いことも、ずっとは続かない―。
辻村深月さんの小説『スロウハイツの神様 上下』感想です。・・・これはすごいですね。感動しました。しかも号泣です。
下巻まで読み終わって評価が高いのがうなずける。読み始めと終わりで感じ方がガラッと変わる一冊。

下巻がものすごく良かった。伏線がすべて回収された!
実は、上巻を読んだ時は 「これはハズレ?」 と思ったんです。・・・途中でやめなくて本当に良かった。
『スロウハイツの神様』あらすじ
必ずラストに号泣する!
脚本家の赤羽環が暮らす アパート「スロウハイツ」。そこには 人気作家チヨダ・コーキをはじめ、様々な人たちが住んでいた。やがて 新しい住人がやってきて・・・。
『スロウハイツの神様』ネタバレ感想文
上巻と下巻の面白さが全然ちがう。・・・なんなんだろう、この差は。
たくさんの伏線が散りばめられていて後半で一気に回収されます。

さすが辻村さんだ。
「二十代の千代田公輝は死にたかった」 に号泣

最終章の 「二十代の千代田公輝は死にたかった」 がとても素晴らしかったです。

この章あっての物語だと感じたよ。
環に会ったときのコウちゃんのひとことに、こんな深い意味があったんだと涙が止まらなくなりました。間違いなく号泣します。
スロウハイツの住人たち (登場人物)
物語は 「スロウハイツ」 というアパートでくり広げられました。主人公は 赤羽環。アパート「スロウハイツ」のオーナー兼、脚本家です。

シェアハウスみたいだね。
藤子不二雄たちが住んでいたトキワ荘をイメージしているようです。住人たちの流しそうめんパーティ (?) シーンは 楽しそうでした。
前半はそれぞれの日常や過去などが描かれています。特におおきな盛り上がりはなく淡々と・・・。

この辺りは、正直、少し退屈だった。
読み終わってみると、ここの部分があるから最後が生かされると気づきました。すべて分かった上でもう一度読み直すと面白いかもしれませんね。
誰もが好きになる、チヨダ・コーキ

この物語には欠かせない人物、千代田公輝(人気作家のチヨダ・コーキ)。
読み終わったときに間違いなくみんな好きになるであろう人物です。私も例外ではありませんでした。

おじさんなんだけど、とても純粋で子どもみたいな人だよ。
初めから好感が持てました。そして最終章を読んでからもっと好きになる。子どもみたいで、でもちゃんと人の痛みを理解してあげられる人です。
彼が言ったひとことが素敵でした。
いいことも悪いことも、ずっとは続かないんです。いつか、終わりが来て、それが来ない場合には、きっと形が変容していく
楽しいときは、それがずっと続けばいいのにと思う。でも苦しいときは、この苦しみがずっと続くような気がする。
「いいことも悪いことも、ずっとは続かないんです」 と言った公輝のことばに救われる気分になりました。

苦しいときに思い出したい言葉。
コーキの天使ちゃん
チヨダ・コーキについては 最終章 「二十代の千代田公輝は死にたかった」 に、彼の人柄が描かれています。
編集者の黒木が面白可笑しくコウちゃんの話をしていたことがこの章に繋がっていく・・・。
いきなり買ってすぐ人にあげてしまった大型テレビのことや、クリスマスに大量に買った 「ハイツ・オブ・オズ」 の高級ケーキのこと。
前半だけを読むと、千代田公輝、ちょっと変わった人?・・・と思うのだけど、彼の行動にはちゃんと理由がありました。

公輝の心には、ずっと 「コーキの天使ちゃん」 がいたんだね。これは恋愛ものだなぁ。
人を想う気持ちは尊いものです。コウちゃんのエピソードひとつひとつに理由があって号泣しました。
好きな作家さんの新刊を読むことは、私にとっても楽しみのひとつです。ときに生きる希望にすらなりえる。

「コーキの天使ちゃん」 の気持ちがわかる。
『スロウハイツの神様 』面白いから下巻まで読もう!
『スロウハイツの神様 』、読後感がものすごく良かったです。すべてがラストに繋がっていくのはすごかった。
ただ、前半にもう少し盛り上がりがあったら良かったのにとも感じました。
最終章 「二十代の千代田公輝は死にたかった」 とエピローグだけがずば抜けて良くて、あとはそれを引き立てる序章のような感じが否めない・・・。

これがもし上下巻ではなくて一冊だったら、そこまで感じなかったのかも。
とは言え、面白かったからおすすめです。必ず下巻まで読みましょう。