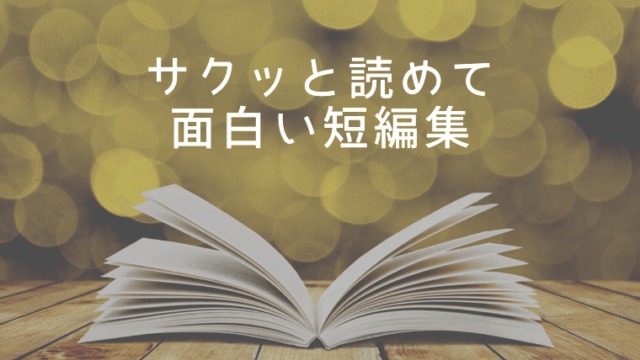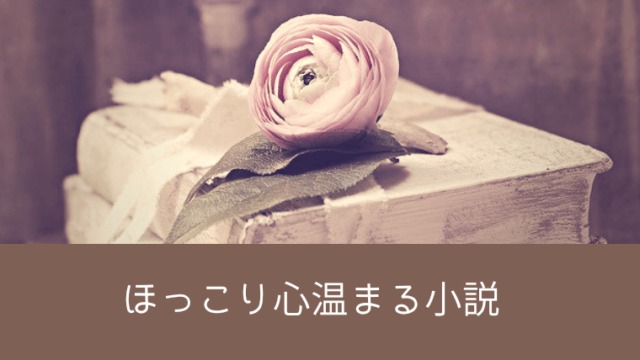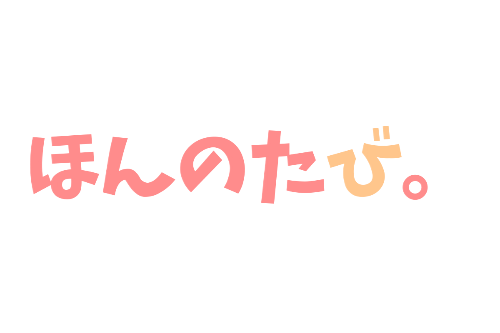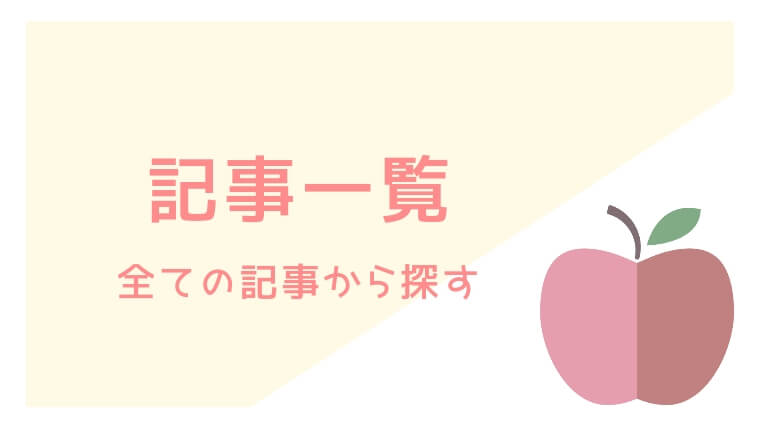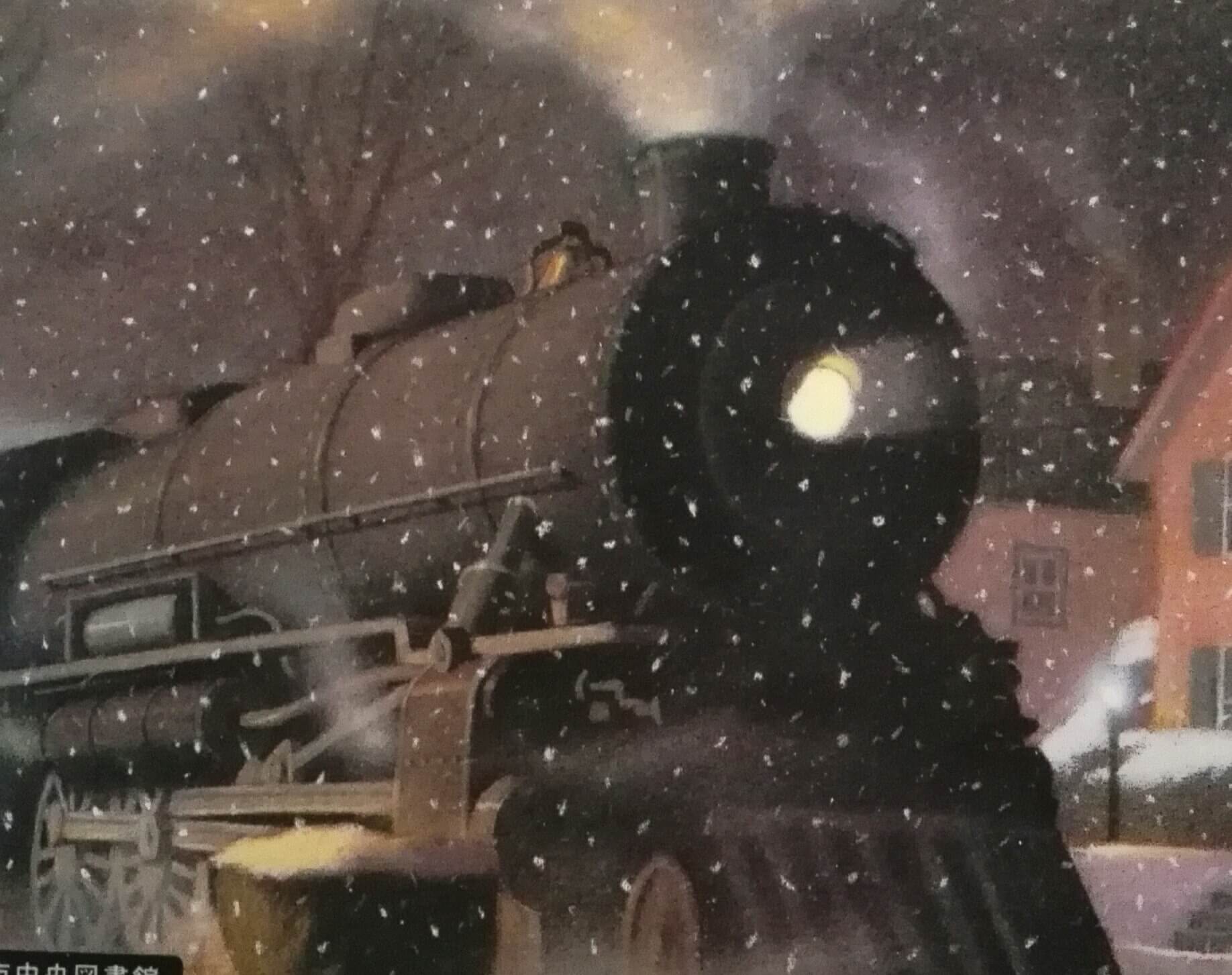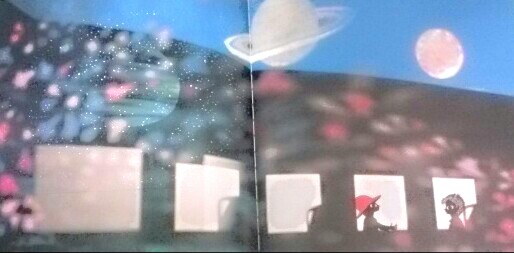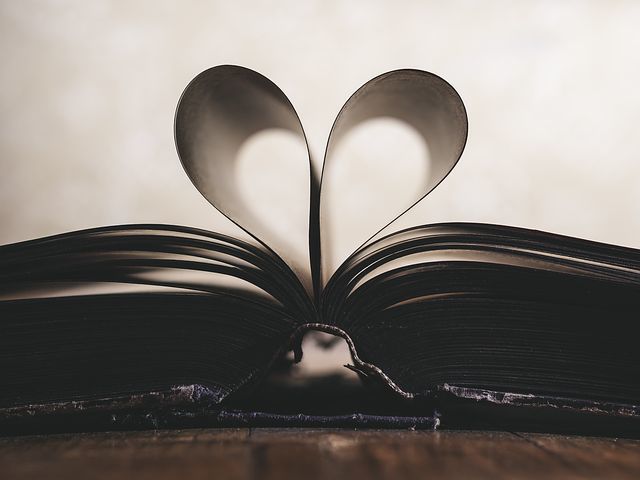『やまなし』あらすじと読書感想文・考察「クラムボン」の正体と宮沢賢治の幸福論

- 教科書『やまなし』あらすじと読書感想文・考察
- クラムボンの正体
- 宮沢賢治の幸福論
- 5月と12月の対比
- タイトルの意味
- 大人と子どもを魅了し続ける理由
クラムボンはわらったよ。
宮沢賢治の童話『やまなし』を読んで考えたこと・思ったこと (考察と読書感想文) です。小学校6年生の教科書に掲載されていますね。
私が読んだのは『もう一度読みたい教科書の泣ける名作』に掲載されている1話。

賢治の幸福論が頭をよぎった。
「クラムボン」の正体など様々な解釈があげられていて、大人も子どもも魅了され続ける物語です。
『やまなし』教科書 あらすじ
宮沢賢治『やまなし』
小さな谷川の底を写した2枚の青い幻灯。季節は5月と12月。5月の昼、2匹の蟹の子どもたちが、青白い水の底で話しています。『クラムボンはわらったよ。』そのとき、1匹の魚が頭の上を過ぎていきました・・・。12月の夜、大きくなった蟹の子どもたちは、あまりに月が明るく水がきれいなので外に出て、しばらくだまって泡をはいていました。そのとき、黒くて円い大きなものが落ちてきたのです・・・。
「クラムボン」 の正体|考察と解説

『やまなし』を読んだときに、誰もが気になることがあるんじゃないでしょうか。
「クラムボン」って何?
実は、賢治の造語「クラムボン」が何かは語られていないんですよね。想像の域をでないけど、ネットで検索すると様々な意見がチラホラ。
- 泡
- カニの母親
- プランクトン

初めて読んだときは泡で、今はプランクトンだと思ってるよ。
『やまなし』に登場する「クラムボン」。川の底にいる幼ないカニの兄弟が下から「クラムボン」を眺めているところから物語は始まります。
『クラムボンはわらったよ。』
『クラムボンはかぷかぷわらったよ。』
『クラムボンは跳ねてわらったよ。』
『クラムボンはかぷかぷわらったよ。』
「かぷかぷわらった」や「跳ねてわらった」などの表現が楽しいですね。ここだけ見ると「クラムボン」は泡のような気がしました。
そこへ魚が泳いできます。
『クラムボンは死んだよ。』
『クラムボンは殺されたよ。』
『クラムボンは死んでしまったよ・・・・・・。』
『殺されたよ。』
楽しそうな光景が一転、「死んだ」「殺された」に変わりました。
泡が割れた?
続く兄の言葉で「クラムボン」は泡じゃなくてプランクトンなんじゃないかと感じました。
『何か悪いことをしてるんだよとってるんだよ。』

プランクトンだと、兄が言った「とってる」という言葉がしっくりくるからだね。
真相はわかりません。泡でもプランクトンでもなく、賢治の世界でのみ存在する生物かもしれないし・・・。賢治にしか答えはわかりません。
でもここでは「クラムボン」はプランクトンということで話を進めていきます。
『やまなし』に描かれた宮沢賢治の幸福論
『やまなし』と言うと必ず「クラムボンは何か」問題がでてきますね。でもそれよりももっと興味深いことがあるんです。
宮沢賢治の幸福論「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」が垣間見えること。

宮沢賢治の小説では、彼の幸福論は外すことができないもの。
『やまなし』も例外ではありません。賢治の幸福論を連想せずにはいられない物語です。
賢治が考える 「みんなのほんとうの幸い」

宮沢賢治が言う「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」。その幸福論は『やまなし』でも垣間見ることができます。
私がこの言葉に初めて出会ったのは『銀河鉄道の夜』でした。
『銀河鉄道の夜』では、「みんなのほんとうの幸い」と「自己犠牲の愛」がセットで描かれています。

サソリのように自分を犠牲にして他者の幸せを願うことは、私にはムリ・・・。
正直、自己犠牲うんぬんは肯定できないけど、『やまなし』でも賢治の幸福論が透けて見えてきました。
5月と12月の対比にみる幸福論

『やまなし』で描かれているのは、5月と12月の川底。2つに抱くイメージは真逆です。
- 5月→「死」を連想。心が落ち着かず不安なイメージ
- 12月→「生」を連想。希望に満ちている
5月では「クラムボン」は魚に食べられ、魚はカワセミに食べられる食物連鎖が描かれていて「死」を連想します。
自然界では当たり前の光景だけど、カニの兄弟にとっては違いました。
『何か悪いことをしてるんだよとってるんだよ。』
「クラムボン」をとって(食べて)いる魚は「何か悪いことをしている」のです。自分が生きるために必要なことが悪いこととされていました。

これは、賢治の「みんなのほんとうの幸い」じゃない行為だからかな。
では、真逆に描かれている12月はどうか。
12月には「やまなし」がカニのいる川に落ちてきます。ちなみに「やまなし」とは山梨、果物のナシですね。
「やまなし」はいい匂いのするもの、熟すと美味しいお酒になるものとしてカニに尊がられている存在。希望に満ちて「生」を連想します。
みんなに幸せをもたらす「やまなし」は「みんなのほんとうの幸い」の象徴のように感じました。

川底にいい匂いをさせて、もう少し待てば美味しいお酒ができる。カニたちの世界では、みんなが幸せ。
「やまなし」は「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」という幸福論に当てはまります。
カニの住む世界は「やまなし」のおかげで幸福になる。5月も12月も真逆ながら、そこには賢治の幸福論が感じられるのです。
なぜ『やまなし』なのか|タイトルの意味

ところで、なぜこの童話のタイトルは『やまなし』なのでしょうか。
5月には「やまなし」は登場しないし、それがでてくるのは12月の最後の方です。「クラムボン」に比べると印象が薄いイメージ・・・。

ぶっちゃけ「クラムボン」でも良いんじゃないの?
5月は「クラムボン」で、12月は「やまなし」。別々にタイトルをつけれそうなくらい、お互いどちらかにしか登場しません。
ではなぜ『やまなし』にしたのか。
「クラムボン」よりも幸福を象徴する「やまなし」をタイトルにすることで希望が感じられる。
これも真相はわかりません。でもカニたちを幸せに導く「やまなし」は、賢治の考える幸福論そのもの。未来の幸福を願う思いが感じられました。
宮沢賢治「みんなのほんとうの幸い」について思うこと
『銀河鉄道の夜』、『やまなし』を読んで再び賢治の幸福論にふれました。
最近思うことがあるのです。
自己犠牲がない世界が「みんなのほんとうの幸い」に近づくということ。

死に繋がる自己犠牲は自己満足だよ。
本人は良いかもしれないけど、その人が犠牲になることで悲しむ人がいます。悲しむ人は幸福とは言えませんね。「みんなのほんとうの幸い」を願うなら自己犠牲がないことが大前提です。
教科書『やまなし』が大人と子どもを魅了し続ける理由
学校の教科書にも掲載されて、今でも様々な解釈が絶えない『やまなし』。それはひとえに、全てが謎のままだからでしょうね。
もしも「クラムボン」の正体がわかっていたら?
とっても知りたいことだけど、想像する楽しみが半減しちゃいます。いくつかの謎が大人と子どもを魅了し続ける理由。

童話や小説もそうだけど、物語には想像する楽しみがある。
想像力が身につく、考察力がつくなど堅苦しいことは抜きにして。ただただ想像する楽しさが味わえるのが『やまなし』の魅力でもあり、物語を読むことの魅力でもあります。